

AIとの共学が開く新しい教育の未来、武庫川女子大学での実践
新たな学びを切り拓く、AIとの共学
7月3日、武庫川女子大学にて、株式会社コンピュータ技研が主導する革新的な授業が行われました。この授業は、若者と中小企業が未来を共に創る「ミライ企業プロジェクト」の一環で、従来の教育方法とは一線を画す新しいアプローチが取り入れられています。AIを活用したこの授業では、学生が主体となりAIに問いかけることで学びを進めるスタイルが特徴です。
新しい教育の必要性
昨今の教育現場では、AI技術の普及に伴い、旧来の「教える・教わる」スタイルからの転換が求められています。コンピュータ技研の松井佑介代表は、「AIが教えるのではなく、AIと共に学びを創る」ことの重要性を強調しています。彼の講義では、学生たちが対話を通じて創造的な問いを立てることで、新たな学びの可能性が探求されています。
授業スタイルの革新
この授業の最大の特徴は、AI講師「AI松井」による対話型の授業スタイルです。AI松井は松井代表の価値観や言葉を基に生成されており、学生が投げかけるさまざまな質問に対して応答します。授業の進行は、AIの回答をもとに講師が補足し深化させることで進んでいきます。これにより、質問に基づいて進行する「ライブ型授業」が実現します。
学生の創造的な問い
授業では学生たちから以下のような深い問いが提示されました:
- - 「AIに仕事は奪われるのか?」
- - 「100年後の社会はどうなっているのか?」
- - 「愛とは何か?」
驚きの学びの展開
授業のクライマックスには、AIが学生との対話内容をまとめ、「希望ある未来の物語」として返すという予想外の展開がありました。このプロセスを通じて、AIとの対話が「答えを求めるのではなく、新たな問いを生み出す」ことの重要性を際立たせました。この新たな学習体験は、学生に対して思考を促し、同時に物語を生み出す機会にもなったのです。
参加者の反響
授業内容はSNSで松井代表から発信され、多くの教育関係者や企業の人材育成担当者から高い関心を集めました。「問いがなければ始まらない」という構造が学生の主体性を引き出し、講師と学生の間にワクワクするような予測不能な展開を生み出したとの反応が寄せられています。その中で、「AIの返答を待つ時間が深い思考を生む」といった意見もあり、多くの参加者がこの授業の新たな可能性に感動していることが伝わってきます。
今後の展望
この実践は、「AIと共に学びを創る」教育として今後の展開が期待されます。これから他の大学や高等学校での導入、企業研修への応用、地域探求学習への活用などが計画されており、問いを起点とした共創型教育の普及が目指されています。
まとめ
今後も株式会社コンピュータ技研の取り組みに注目し、AIと人をつなぐ新たな学びの形が広がっていくことを期待しましょう。この革新的なアプローチは、教育の未来に大きな影響を与えることでしょう。



関連リンク
サードペディア百科事典: 武庫川女子大学 コンピュータ技研 ミライ企業プロジェクト
トピックス(その他)


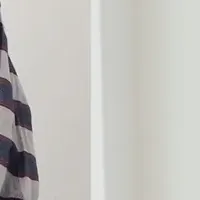
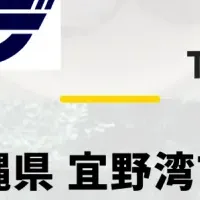




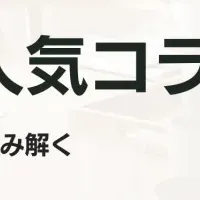

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。