

AI技術で低線量CTの肺結節検出能力が向上 - 長崎大学病院の研究成果
AI技術による肺がん検診の新たな進展
2025年11月、東京で開催された日本肺癌学会学術集会において、長崎大学病院の研究チームが画期的な研究成果を発表しました。この研究では、AIを活用した肺結節の検出感度が大幅に向上したことが示され、多くの医療関係者に注目されています。
研究の背景
今回の研究は、プラスマン合同会社が開発した「Plus.Lung.Nodule」というAIシステムを用いて実施されました。研究チームは、75例の低線量CT画像を用いて、AIの導入前後で読影医の検出能力を比較しました。このスクリーニングにおいて、結節あり61例と結節なし14例が評価されました。
今回の研究成果
研究の結果、低線量CTを用いた場合の肺結節検出感度が劇的に向上したことがわかりました。具体的には、全ての読影医による症例毎の感度は87.8%から93.8%に向上し、結節毎では52.3%から73.8%に改善。この結果は、AIを利用することで結節検出能が41%向上したことを意味します。
特に注目すべきは、AI支援を受けた非専門医の症例毎感度が93.4%に達し、AI未使用の専門医91.0%を上回った点です。これにより、AI技術が医療現場での重要な支援ツールとなる可能性が示されました。
読影医の経験レベルを超えた有用性
研究では、経験豊富な専門医と非専門医の両方が対象となり、AIの効果を検証しました。その結果、専門医の結節毎感度は61.4%から78.7%に改善された一方で、非専門医は45.1%から71.6%に改善し、著しい向上が確認されました。これにより、AI技術が読影医の経験や専門性に関わらず、全体的な診断能力を高める可能性があります。
AIの実臨床での統合
研究においては、AIを臨床現場に統合する2つの手法が評価されました。1つはセカンドリーダー型で、医者が単独で読影した後にAIによる確認を行う方法。もう1つはコンカレントリーダー型で、AIをリアルタイムで参照しながら診断を行う方法です。いずれの手法でも診断精度が向上し、特に経験の浅い医師においてさらなる効果が見られました。
結節タイプ別の性能向上
肺結節は、Solid nodule(充実性結節)、Pure GGN(すりガラス影)、Part-solid nodule(部分充実性結節)の3つのタイプに分類されます。本研究では、全てのタイプにおいてAIの支援による検出感度の向上が確認されました。たとえば、充実性結節では感度が51.9%から72.1%に改善され、すりガラス影は44.8%から73.5%に向上しました。
専門家の意見
本研究の意義について、長崎大学の芦澤和人教授は、「AIが偽陽性を増やさないことは、読影医の業務負担を軽減することを示しています。本研究は、医療現場におけるAIの実用性を示す重要なエビデンスとなります」とコメントしています。また、プラスマン合同会社の代表の大塚裕次朗氏も、独立した臨床研究での有効性の検証に喜びを表し、患者の早期発見への貢献を強調しました。
まとめ
今回の研究は、AI技術が肺がん検診の現場でどのように役立つかを示す重要な一歩となりました。今後、低線量CTスクリーニングの普及が進む中、AI支援が医療の質を向上させる役割を果たしていくことでしょう。医療現場のさらなる発展に期待が寄せられています。

トピックス(その他)


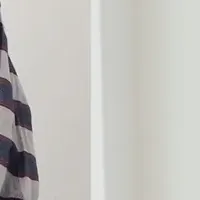
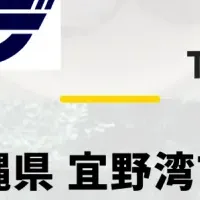




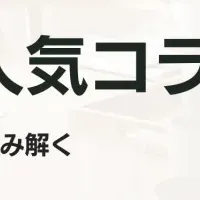

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。